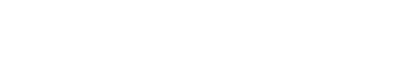理事長対談
対談日:2020年6月11日
場所:精三会館

鶴岡市・三川町・庄内町のエリアに関しても新型コロナウイルス(以下 ウイルス)の影響により、各分野において軒並み大変な状況になっていくと思われます。加藤鮎子代議士からはなかなか地元に帰ることのできない中、このような機会をいただきました。今後、感染の第2波・第3波が危惧されていますが、本日ご参加いただきました各団体の、これから時代を担うリーダーの方々より貴重な意見を伺って代議士にお伝えしたいと思います。

加藤 鮎子代議士(東京からリモート)
皆様お忙しいところ、WEB意見交換会の参加ありがとうございます。ウイルスの状況下でこの3~4か月間、生活スタイルが変わり、色んな意味で激変する環境下にあったと思います。特に皆様は各団体の代表でいらっしゃいますので、ご自身のことばかりではなく所属するメンバーを心配し、あるいはなかなか情報共有ができず身動きがとれない時期もあったのではないかと推察しておりますが、その辺りも伺いたいです。私自身は国会会期中にコロナ禍の佳境に入ったので、突如として状況が変わり、毎週金曜日には地元に帰り、月曜か火曜には上京するという生活をしていたのが、自宅に帰れなくなりました。秘書とは打合せをしますが、緊急事態宣言に入ってからは、秘書も地元をまわることができず、事務所にお顔出しされる方々も動きが取れなくなり、とにかく情報が少ないという状況の中にありました。ただ、SNSなどで直接連絡をいただく方やメールをくださる方がたくさんいて、窮状を訴えてくる方々の切実な状況から本当にとんでもないことになっていると感じております。
政府の動きが非常に遅いということへの苛立ちが、自民党内にもありました。
私は環境省の政務官ではありながら、当初、政府の動きの情報が入ってこない状況でした。ウイルスに関しては、主に厚生労働省、経済産業省が対策に当たっており、そのため環境省には情報が即座には入ってきませんでした。
私は、若い世代からは偏った声しか聞いてないように思います。あまり青年団体の長とは話をする機会が無かったので、大変貴重な機会だと考えます。全体感のある意見を聞き、政策に反映できるよう力を尽くします。
【活動について】
2020年度 鶴岡商工会議所 青年部 金野 隆行会長

鶴岡商工会議所青年部としてはコロナ禍でも事業をやるということを予定していたのですが、大中小問わず経営者が多いので、そういった方々とお話をしながら、今、何が一番必要なのかを考えました。それは、持続、つまり会社を潰してはならないということです。
特に零細企業などはウイルスをきっかけに廃業するところもあると聞いていますので、我々が出来る限り力になれるように体制を整えております。具体的には、まずは情報提供です。従来からの商工会議所の広報だけではなく、SNSを活用して臨機応変に発信しています。部員一人一人に寄り添いながら、どんな小さな情報であれ必要となると考え、そういった情報発信をしています。従来の青年部の活動は何もできていないのが事実ですが、日々の状況を精査しながら変化に対応していかないといけませんので、状況確認をしながら進めております。
出羽商工会青年部 佐藤 芳彦部長

出羽商工会は庄内南部の旧7市町村(鶴岡、温海、櫛引、羽黒、藤島、大山、羽黒、三川)が一体となっており、各地域の後継者が加入している団体です。新型コロナウイルスに関して、会員の中には飲食業や観光業に携わる方が相当数いらっしゃいます。現状では会員事業所が1317ありますが、少なからずコロナの影響を受けている事業所が約350件あります。
また、私が住んでいる温海温泉は、観光業が主体となってる地域です。去年6月の山形県沖地震の被害もあり、その復旧途中でウイルスの影響を受けて厳しい状況です。
従来の青年部事業ですと、例えば未来塾という次世代を担う子供達を集めるイベントなども今年は開催できません。今のところは、感染予防の啓発と各自の事業につき、商工会の各種支援制度を活用しながら、既存事業所の存続に努めて頂くように会員の皆様にお話ししてます
公益社団法人鶴岡青年会議所 2020年度 佐藤 友介理事長

鶴岡青年会議所は現在76名のメンバーがいて、単純に言うと76の企業がいます。OBも含めると約1000社以上あり、普段はその深い絆で事業を行っておりますが、ウイルスの影響で、多くの事業が中止となりました。例えば赤川花火大会です。実行委員会が関係各所と日々協議を重ねていたんですが、状況を鑑みると難しいだろうという判断です。
既に決まっていた年間スケジュールを、簡単に言うと白紙にし、新型コロナウイルスの対策関連事業に切り替えました。予算を変更するために緊急対策会議を開き、最近では佐藤天哉専務理事の発案により、鶴岡市と三川町の学童保育施設に消毒液や薬用石鹸など、感染予防で必要なものを提供するとともに、より重要視されるSDGsの教育事業を行いました。
この事業を詳しく説明させていただきます。事前のヒアリングにおいて、各小学校は教育委員会が主体となって必要なものを補充、提供してもらえるが、学童保育施設はそれぞれの学童保育施設が主体となって動かなければならず、物品の調達も自分達でしないといけない。しかしながら、ドラッグストアに行っても無い。インターネットで買おうとしても高い。本当に苦労している実情を伺うことができました。今何が求められているのか事前に調査を行い、アルコール消毒液や手洗いを子供達に習慣付けさせるための薬用石鹸が必要であると判明しました。学童施設は鶴岡市内で24か所、三川町内で1か所、計25か所あります。全ての施設に鶴岡青年会議所メンバーのマンパワーで、3日間で配布することができました。
青年会議所としても素晴らしい運動ができているなと改めて実感できましたし、学童保育施設からは本当にありがとうという心の声をいただけたので、それを活力にして、今後も価値のある事業を考え、行動していきたいと思っています。
一方で私が心配しているのは、活気が薄れていくのではないかということです。赤川花火大会然り天神祭然り、様々な夏の風物詩、イベントが無いわけです。学童の皆さんも音楽コンクール、絵画コンクールなど様々なイベントが中止になり、今後運動会や何か事業を行うとしても、三密やソーシャルディスタンスを考慮にいれなければならない。例年と違う雰囲気になり、活気が薄れてくるのではないか、そこが心配です。青年会議所として今後の課題だと感じるのは、街の活気を新しい生活様式に沿った形でどのように取り戻していくのかということです。
【ウイルス対策事業について】
金野会長 :
4月16日に持続化給付金や融資制度など、国の支援事業の情報を会員内で勉強をするセミナーを予定していたのですけれども、どうせするならライブ配信しようということで、4月17日に新型コロナウイルス対策支援事業の勉強会をしながら、ライブ配信しました
かなりの反響があり、瞬間で約2,000人視聴していただけました。この取組みは全国的にも早かったため、YBCなどのメディアや商工会議所の全国組織でも紹介されまして、それに続けと他の地区の団体も同じように真似てくれたのは非常に良かったなと思いました。
ただ、制度がその都度変わるために、早いと1週間前に覚えた知識がまた変わってしまうということもあります。経営者によっては、その情報のズレは致命的です。
持続化給付金についても、早い段階で給付を受けている企業もあれば、用件を満たさず給付申請が出来ていない企業もある。業種や規模によっては、その要件を満たすまで業績が悪化してしますと給付を待たずに潰れてしまうところもある。地方自治体独自の支援策もありますが、それでも足りない場合もある。これは、ことあるごとに集まった際に会員から情報収集を行っている中で出てくる実情です。会員企業を守るというのが、現状の我々としての使命ですので、もっと経営者の声を集めて、情報の共有を進めていくことが活性化の一助になる、そういった想いで活動しています。
佐藤部長:
出羽商工会本体の事業をなるべくお手伝いするということで動いております。ウイルスの相談窓口も開設し、ウイルス対策の融資、雇用調整助成金、持続化給付金、令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金のウイルス特別対応型の申請などを活用して各事業所の継続維持を最優先に進めております。
また、商工会の県組織で主催している地域経済元気回復キャンペーンが5月27日から6月30日まで開催されていました。飲食業、観光業の他、生活関連サービス業、理容業やクリーニング業なども対象なっているキャンペーンで、500円以上購入すると応募用紙をお渡しして、10,000相当、5,000円相当、3,000円相当の計600本の景品が当たるキャンペーンを開催しました。
他には、Dewaキッチンというデリバリーやテイクアウトの特設サイトを開設して鶴岡市内と全7支部の参加事業所を紹介しています。
特設サイトはこちら→ http://dewa-shokokai.com/dewakitchen
全国の青年部連合会としても、ニッポン全国お取り寄せ応援フリマ情報局を立ち上げ、商工会会員以外の方でも参加できるようにし、ゴールデンウィークの自粛期間中に困っているお店が全国に宣伝できるようなSNSページを作りました。
Facebookページはこちら→
今のところの取り組みは以上になります。
【今後の未来を語り合う】
加藤代議士:
各団体の取り組み状況を伺い、本当に頭の下がる思いです。個人的なことからご自分の会社のことまで、様々大変な状況の中で団体として決断しなければならないことを決断したり、困っている人に手を差し伸べたり、会員の皆さんの為に知恵を絞って活動されたり、本当に素晴らしいと思います。
こういうところはすぐにでも直した方が良い、ということも耳にしているのではないかと思います。そういうことがあればぜひ教えていただきたいです。
例えば皆さんからの声が政治に届くという点では、持続化給付金の対象をもう少し広くしてもらえないかという話です。地域の為、例えば鶴岡では荘内神社はご寄付や事業で成り立っている部分もあるにも関わらず、持続化給付金の対象としてはばっさり切られてしまっているというのがあり、賛否両論ありますが、お寺関係・神社関係の方々を入れるか入れないかという議論がありました。
また、昨年事業を立ち上げたばかりで昨年と今年とで売上の比較が出来ない、でも真面目にやっていて、少なからず投資してスタートしたばかりなのにもはやショートしかねない、しかも実績が少ないので融資もなかなか厳しいなどのお声もいただいています。
制度的に真面目な人が救われていないというものがあれば伺いたたいですし、他方で心配しているのが非正規の方々、例えばシングルマザーの方が、どういった援助を求めていいかもわからず、目の前のことでいっぱいで本当だったら得られる支援もうまく得られていないという方々もいるでしょう。
海外では個人には給付金を配りますが、企業には冷たいので、基本的には解雇、その代わり解雇された人が国から救われて、また状況が良くなったら雇いましょうねという仕組みになっている国もあります。一方で日本では、企業に対して支援し、従業員のことを守ってくださいとやっているので経営者の方々、それを支える商工会議所、商工会、青年会議所の皆さんは大変だとは思いますが、その活躍に感謝申し上げます。
皆さん子育て世代だったので、休校があって大変だったのではないですか?

公益社団法人鶴岡青年会議所2020年度 佐藤天哉専務理事:
学校の休校中が大変でした。何もイベントが無く、家にずっといるため体も動かせないのでストレスが溜まっている時期がありました。
加藤代議士:
金野会長はサッカーのスポ少の関係者でもありますよね?
金野会長:
サッカークラブの理事をしています。集まって練習をやるのも反対され、遠征にも行けず、小学生のストレスはあります。
加藤代議士:
甲子園も早い段階で中止になりましたが、交流イベントをやるくらいなら、大会をやればよいのにと思うこともあります。なぜなら、3年生にとっては一生に一度ですから。一方で赤川花火大会の中止は英断だったと思います。鶴岡市外だけではなく山形県外からも沢山の人が来て密になるのは避けられないでしょうから。
今後は各イベントの再開の基準というのが難しいと思います。スポーツイベントも含めて、イベント毎が中止になると、企業活動はもちろん、どんどん活力が無くなっていく。全体が暗くなってしまうと影響が大きいので、どこかで再開のタイミングを考えないといけないと思います。
イベントを開催したことによってクラスターが発生した時のリスクを考えると、開催しないという判断になる訳ですが、それによって全体が暗くなってしまうとそれもまた影響は大きい。だから、どこかで再開しないといけないだろうと思います。
例えば、飲み会や懇親会の今の状況はどうでしょうか。表だってはやらないが声を掛けあって開催している状況なのか、飲み屋街は人がいるのか、私は行けてないので現場の実情がわかりません。
佐藤理事長:
総会などの会合が一切開催されていないので、その後の懇親会という形は開催できていないものと思います。けれども、人数を絞って感染対策を十分にした上で、飲み会をやる人達は出てきました。ただ、以前の活気には戻っていないので、飲食店など大変なところは多いです。
金野会長:
運転代行業者のデータでは4月3日から売り上げが1日約1000円しかない日が続いていました。これが緊急事態宣言解除になった6月11日以降徐々に回復してきて、6月15日のスナック営業が解除になってからは、だいぶ人が動くようになりました。週末は仲間内で、平日は会社関係で動いていることが多いです。
加藤代議士:
徐々に動いてきているのですね。
佐藤部長:
鶴岡市では「プレミアム付飲食券」が配られ、山形県の「県民泊まって応援キャンペーン」では、旅館に泊まる際に補助が出るなど、様々な取り組みが始まっています。
加藤代議士:
是非話を伺いたいところとしては、事業と感染対策のバランスをどう取っているのかです。厚生労働省でガイドライン作成のひな型を用意していて、それに基づいて各業界団体等でガイドラインを作成していただいています。ただ、このガイドラインが実際どのようなものなのか、現場に即したものなのかどうか。感染対策を厳しくしすぎても、営業に影響が出てくるのではないですか?
佐藤部長:
国や県で示しているガイドラインだと飲食の際、人と人との間の間仕切り、お酌をしない、喋らないというのが基本になっていて、これは我々にとっては非常に厳しい。一方鶴岡市では、食文化創造都市つるおか元気プロジェクト(※1)や飲食店、小売店向けの安全推進プロジェクトが立ち上がりました。山形県内の市町村では鶴岡市が先駆けてやっています。ガイドラインに沿った対策の他に、お店とお客さん双方が感染症対策をして安心・安全を進めましょうという取り組みです。積極的に取り組んでいるお店には、そのことを知らせるステッカーを掲示していただいたりもしています。
加藤代議士:
みんなで意識を共有した方が安心しますね。安全策だけにならずに、みんなで意識を統一しながら頑張ろう!という雰囲気になると良い取り組みになると思います。素晴らしいですね。
海外の状況と比較すると、日本の感染者数や感染者の伸び率は比較的低い傾向にあります。
私の考察では、日本人の性格的な面として、集団心理が非常に強いという特徴があり、周りに迷惑をかけてはいけないだとか、一つの集団を守ろうとする力だとか、マナーとかエチケットを含めた感染対策にもそういった心理が働いていて、国民全体の意識の高さに繋がっています。それが少なからず、新型コロナウイルスの感染拡大防止に繋がっていると思っています。
また、これは食文化なり民俗学的なところに起因するのかもしれませんが、例えばインフルエンザの流行の際、海外で流行している型と日本で流行している型とが違っていて、海外で流行しているものには日本人は既に何らかの抗体を持っているという研究結果が出ています。つまり今日本を含め世界各国でワクチン開発や治療薬開発が進められていますが、そういったものが完成する前に、日常生活の中で抗体が生まれ、日本ではいつの間にか収束しているという可能性もあるのかなと思います。
緊急事態宣言は解除されましたが、政府としては第2波は必ず来ると予測して備えています。それが、秋なのか冬なのか、はたまた明日なのかはわかりませんが、いつまでも心配ばかりして、経済を止めてしまっていては、体力の無いところから本当に潰れていってしまう。今はそれを避けることは最優先に考えるべきだと私は考えています。
ですから、新しい生活様式の中で、3密を避けた飲み会とか、テレワークやウェブ会議とか、出来るところから少しずつでも再開していくことが大切だと思います。それに指針が必要ならば、各地方自治体で指針を示したり、市民の行動を促すことも大事です。そこを促すのが政治の役割だと思います。
もちろん今も大変なのは間違いありませんが、特に我々のような若い世代は、withコロナと言われるように、新型コロナウイルスとどうやって付き合いながら、どのような山形県、鶴岡市にしていくかを考えなければなりません。そして、新型コロナウイルスが収束した後、どのような山形県、鶴岡市にしていくのかを考えることも大事だと思います。
少なくとも国は国家ビジョンを新たに描き直す作業を始めています。現状、新型コロナウイルス対応が最優先ですので、まだ表に出ていませんが、先手先手で描かないと後れを取ってしまいます。
それを考えると山形県はみんなが頑張ったことで、7月まで死者が出ることもなく傷が浅く乗り越えられているだけに、次の大きな変革をするぞ!という機運に如何に乗せられるかどうかは大きな分かれ道だと思います。
世界各国や被害が大きかった都道府県は働き方に対しての変化が大きく、大企業の中では、新型コロナウイルスが落ち着いてもそれ以前と比較して30%の出社率を続けよう!という方針を打ち出す会社が出てきていています。
そうなると働き方の効率化が早いスピードで進んでいき、行政もマイナンバー制度を含めて、それに追いついていかないといけません。IT化、リモート化などの効率化がかつて想定していたスピードより速いスピードで進んでいくでしょう。
そうなると地方と中央の格差が広がるのではないかと懸念しています。中央が発展するのは良いことですが、新しい変化に対して山形県がどれだけ一緒に変化していけるか、更には独自で長所を伸ばしていくことも考えなければ、その瞬間に格差が広がってしまうと危機感を持っております。
ですので、みなさんのような若手の経営者や経営幹部の方々が自分の会社で取り組んでいることや、今後考えていることがあれば伺いたいです。
佐藤理事長:
本日は皆さんお忙しい中ありがとうございました。このように、各青年経済団体の足並みが揃って動くことが、今まではなかなかできませんでしたし、加藤代議士ともお話しできる機会となり有意義な時間となりました。
加藤代議士から、県境での検温の取り組みを始め、山形県知事とタッグを組んで動いているお話がありましたが、これからもそういった国と地方の繋がりは重要です。加藤代議士は様々な地域の成功事例が情報として入ってくると思います。この地域をより活気のある地域にするために、みんながアイデアを出し合って頑張ってはいますが、そういったアイデアというのはひらめくのが難しいものです。ですから、他の地域ではこうやっているというのを是非ご教示いただいて、それを我々の地域に合ったスタイルに昇華させていく、こういったプロセスも必要になると思います。
私は、国の政策には高い評価をしています。持続化給付金や特別定額給付金、他にも融資制度や産業別の支援制度。例えば10万円の給付も非常にありがたいと思います。
一方で、今回の新型コロナウイルス対応での支出がいつか、我々のような次世代に負担として降りかかってくるのではないかと危惧しています。そしてこの解決策については、みなさんの立場で様々なことを考えているとは思いますが、決して思考を止めること無く、胸を張って自慢できる街に、国にしていかなければならないと思っています。
最後に、出羽商工会青年部 佐藤 芳彦部長のお店「きっちんふーずカスミヤ」さんのプリンを頂戴し、大変美味しくいただきました。ありがとうございました。

きっちんふーずカスミヤ
住所:999-7204 山形県鶴岡市湯温海甲92
電話:0235-43-4163